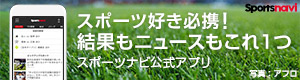ルール
基本ルール
F1とは
F1とは、「Formula One(フォーミュラ・ワン)」の略である。フォーミュラとは英語で「規格」や「形式」を意味し、定められた規格に沿って製造された4輪オープンホイール(フォーミュラカー)で戦うレースの中でも、F3、F2といったカテゴリーの最上位にあたる、まさに世界最速を競うものだ。
グランプリ(GP)と呼ばれるレースを世界各地で開催し、GPごとに優勝者が決まる。予選で決勝のグリッド順を決め、先頭からスタートできるグリッドをポールポジションと呼ぶ。また、GPによってはスプリントと呼ばれる決勝より周回数の少ないレースを組み込むことがある。決勝で10位以内、スプリントで8位以内に入ったドライバーにはそれぞれポイントが与えられ、年間獲得総ポイントでワールドチャンピオンを決定する。
各チーム2人の正ドライバーを擁し、そのコンビの総合ポイントで、年間のコンストラクターズ部門の優勝チームも決める。親会社が自動車メーカーであれば、自分たちの技術力を示すことになり、スポンサーについてチーム名に自社ブランドを冠するだけでも、世界中への大きなアピールにつながる。
マシン開発などにつぎ込まれる資金は膨大で、財政力がチームの力を左右し得る。マシンの性能が大きくものをいい、最速で時速300キロを超えるマシンを操るドライバーには超人的な技術と体力が要求される。まさにチームの総合力で世界の頂点を争う究極のレースだ。
エンジンのルール
F1で勝敗を分ける大きな要素となるのが、マシンの心臓であるエンジンだ。その開発やシーズン中の修正が、結果を大きく変えることもある。
2014年からルールが変更され、V6ターボエンジンとERS(エネルギー回生システム)が組み合わされたハイブリッドシステムが導入された。このシステム全体を「パワーユニット(PU)」と呼ぶ。
PUは内燃エンジンなど、さらに細かい部位に分かれる。これら構成要素を交換できる数は決まっており、その上限を超えると決勝でのグリッド降格などペナルティが科される。ただし、シーズンの早い段階であえてペナルティを受けて、その後のグランプリを有利に進めることもある。
PUの交換制限数は昨シーズン緩和されたが、今シーズンから再び引き下げられることになっている。
タイヤのルール
F1では、タイヤ戦略も勝負を分ける大きな要素となる。ルールの中に、タイヤの使用も組み込まれているからだ。
使用されるタイヤは、硬さが分かれている。主に路面が乾いているときに使用される「ドライタイヤ」は6種類あり、そこからレースごとに使用される3種類が決められ、柔らかいものから順にソフト、ミディアム、ハードと呼ばれる。路面が濡れているときに使用される「ウエットタイヤ」は、溝の浅いインターミディエイトと、深溝のウェットに分かれる。
タイヤは柔らかいものほどグリップ力が高くなるが、耐久性は低い。硬いタイヤは、その反対だ。
ただし、レースではタイヤだけではなく路面コンディションも考えなくてはいけない。暑い場所でのレースでは消耗が激しくなるし、コースによって向き不向きがあるからだ。
また、決勝では1回以上のタイヤ交換が義務付けられており、2種類以上のタイヤの使用が義務付けられている。予選から、与えられたタイヤをどう使っていくかも、大事な戦略になる。天候の変化に合わせたタイヤの変更、あるいはタイヤ交換の回数をどれほどにするかが、結果を大きく左右してくる。
タイヤの交換はわずか2~3秒で完了する。ピットストップで順位の交代もあり、1000分の1秒を争うレースにおいては少しの遅れがレースに大きな影響を与える。
車体のルール
F1の車体は、最先端の科学の結晶だ。少しでも速く走るマシンを作るべく、エンジニアたちが研究に没頭する。
車体のデザインは美しいだけではなく、マシンを地面に押し付ける空気の力を生むなどの効果をもたらす。このダウンフォースを得ることで、コーナーを機敏に走り抜けることが可能となる。一方で、空気抵抗を少なくすれば、ストレートでのスピード向上につながる。エンジンの特性などあらゆることを加味して、デザインが決定される。
レースの展開を大きく影響し得るため、車体についても幅、高さ、重量など細かくルールが設定され、毎年変更も行われる。近年では2022年にF1マシンのシャシー自体でダウンフォースを発生させる「グラウンドエフェクト」が解禁され、チームの勢力図に大きな影響を与えている。